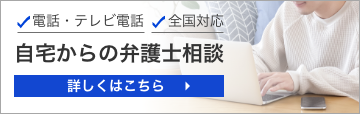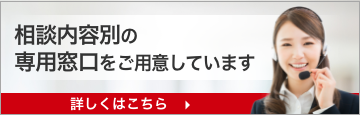能力の低い社員への対応は? 解雇する際の注意点を弁護士が解説
- 労働問題
- 能力の低い社員
- 対応

能力の低い社員(従業員、労働者)がいる場合、どのように対応すべきか悩んでいる方は少なくないようです。該当の社員により大きな損害が出ている状況が続いているケースでは、解雇を検討することがあるかもしれません。
しかし、日本の解雇規制は厳しく、能力の低い社員でも安易な解雇は違法と判断されるおそれがあります。弁護士のアドバイスを受けながら、状況を改善できる方法を慎重に検討しましょう。
本コラムでは、能力の低い社員がいる場合にどう対応すべきかについて、ベリーベスト法律事務所 池袋オフィスの弁護士が解説します。
1、能力の低い社員は解雇できる?
能力の低い社員(ローパフォーマー社員、問題社員)であっても、安易に解雇すると違法と判断される可能性が高いです。著しく能力が低い場合は解雇が認められるケースもありますが、有効に解雇できるかどうかを慎重に検討しなければなりません。
-
(1)能力の低い社員の具体例
能力の低い社員によく見られる特徴としては、以下の例が挙げられます。
- スキルや知識が他の社員よりも大幅に劣っている
- 上司の指示を聞かない
- 何度指導してもミスがなくならず、能力が向上しない
- コミュニケーション能力が著しく低く、他の社員と適切に意思疎通ができない
このような能力の低い社員は、会社に貢献するどころかマイナスをもたらすおそれがあります。会社としては、何らかの方法で対処したいところです。
-
(2)能力の低い社員でも、安易な解雇は違法の可能性が高い
能力の低い社員に辞めてほしいと考えても、安易に解雇するのは違法の可能性が高いので注意が必要です。
一般的に「懲戒解雇」とは、重大な問題行為などの結果、解雇を言い渡すケースを指します。他方で、業務能力不足など、懲戒ではない理由で解雇するケースを「普通解雇」と区別されます。能力不足を理由に行う解雇は、「普通解雇」に該当する可能性が高いでしょう。
懲戒解雇や普通解雇を行うためには、以下の要件を満たさなければなりません。
なお、いずれも解雇制限規定に抵触しないことが前提となります。① 懲戒解雇
- 就業規則上の懲戒事由に該当すること
- 懲戒解雇が就業規則に定められていること
- 労働者の行為の性質、態様その他の事情に照らして、懲戒解雇をする客観的に合理的な理由があり、かつ解雇が社会通念上相当と認められること
② 普通解雇
- 労働契約または就業規則に定められた解雇事由に該当すること
- 普通解雇をする客観的に合理的な理由があり、かつ解雇が社会通念上相当と認められること
特に、解雇に客観的合理性と社会的相当性を求めるルールは「解雇権濫用の法理」と呼ばれています。これは「会社の解雇する権利を濫用してはいけない」という考え方で、解雇には正当な理由が必要で、社会的に見ても妥当でなければならないというものです。
このルールは厳しく適用されるため、簡単に解雇すると違法になる可能性が高いので注意が必要です。 -
(3)著しく能力が低い社員は、解雇が認められることもある
社員の能力が他の社員に比べて著しく低く、業務に対応してもらうために必要な水準に達していないだけでなく、改善の見込みがない場合は、解雇が認められることもあります。
たとえば以下のようなケースでは、社員を有効に解雇できる可能性があるでしょう。- 単純なミスを何度も繰り返しており、丁寧に指導を行ってもまったく改善の兆しがない
- 重大なミスを連発し、会社に対して多額の損害を与えた
- 懇切丁寧に教えても仕事をまったく覚えず、どのポジションでも活躍できる見込みがまったくない
能力不足を理由に社員を解雇しようとするときは、能力不足の程度や実際に会社が被った損害を、客観的な根拠に基づいて説明できるようにしておく必要があります。可能な限り正確かつ具体的に、「同じミスを3か月間で10回繰り返し、お客さまからの契約破棄が5件あった」など、事実を示せるようにしておきましょう。
他方で、できる限り改善指導を尽くし、解雇を回避できるように努めることや、その履歴についても説明できるようにしておくことが大切です。
2、能力の低い社員への対応ポイント
能力の低い社員が業務や周囲に悪影響を及ぼしている場合には、会社は以下のような対応を行いましょう。
-
(1)本人に問題点を伝えて、改善指導を行う
現時点では能力不足でも、本人が問題点を自覚すれば徐々に改善していく可能性があります。
上司などから本人に問題点を伝えて、改善を促しましょう。また、上司などが定期的に面談を行い、改善の方法を本人と話し合うことも効果的です。 -
(2)配置転換を検討する
業務への向き不向きは、人によって差があります。能力不足に見える社員も、今の業務が不向きであるだけかもしれません。
配置転換をして別の業務を経験させれば、自分に合ったポジションが見つかり、能力を発揮してもらえる可能性があります。人が足りない部署や、良いメンターがいる部署などへの配置転換を打診してみましょう。 -
(3)段階的に懲戒処分を行う
注意すれば防げるミスを連発している社員に対しては、懲戒処分を行うことも検討すべきです。
ただし、いきなり懲戒解雇のような重い処分を行うと、懲戒権または解雇権の濫用によって無効となってしまうおそれがあります。
まずは戒告やけん責などの軽い懲戒処分を行うのが安全です。改善が見られなければ、減給以上の懲戒処分への段階的な引き上げを検討しましょう。
3、能力の低い社員を解雇する際の注意点
能力の低い社員を解雇しようとする際には、社員とのトラブルを防ぐため、以下のステップを踏みながら慎重に対応しましょう。
-
(1)事前に十分な改善指導を行い、その記録を残す
社員を解雇する場合は、それが第三者から見てもやむを得ない判断だったことを説明できるようにしておく必要があります。
能力不足を理由とする解雇は、事前に十分な改善指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見られなかったときに認められる余地があります。
上司などによる定期的な面談など、能力不足の社員に対して具体的な働きかけを行い、その内容を記録に残しておきましょう。 -
(2)退職勧奨を試みる
解雇に関する厳しい規制を避けるためには、能力不足の社員と話し合い、合意してもらったうえで退職してもらうのが安全です。タイミングを見て退職勧奨を行いましょう。
ただし、社員が退職勧奨をすんなり受け入れるとは限りません。
退職勧奨を拒否された場合は、退職金を上乗せするなど、社員にとってのメリットを提示しましょう。退職を受け入れてもらえる可能性があります。
会社としては、退職勧奨を拒否されることを想定して、何段階かに分けて条件提示を行うのが賢明です。 -
(3)解雇の要件を満たしているかどうかを慎重に検討する
やむを得ず能力不足の社員を解雇する場合は、解雇の要件を満たしているかどうかを十分に確認しましょう。
具体的には、以下のようなポイントを確認することが求められます。- ほかの社員に比べて、能力が著しく劣っている
- 十分な改善指導を行ったか
- 改善の見込みがまったくない
- 配置転換をしてみたが活躍できる余地がない
解雇を避ける余地があるにもかかわらず、安易に社員を解雇すると、不当解雇を主張されてトラブルに発展するリスクが高まるのでご注意ください。
-
(4)解雇予告または解雇予告手当の支払いをする
社員の解雇を決定した場合は、原則として30日以上前に解雇予告を行いましょう。
解雇予告をしないか、または予告期間が30日未満である場合は、解雇予告手当を支払わなければなりません。支払うべき解雇予告手当の金額は、以下のとおりです。・ 解雇予告をまったく行わなかった場合
30日分以上の平均賃金相当額
・ 解雇の予告期間が30日未満の(たとえば解雇日の10日前に予告した)場合
30日から予告期間分を短縮した日数分以上の平均賃金相当額(この場合は20日分の給与に相当する金額)
なお、労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇するときは、労働基準監督署長の認定を受けた場合に限り、解雇予告および解雇予告手当を支払う義務が免除されます。
解雇予告または解雇予告手当を支払う義務を怠ると、労働基準監督署による是正勧告や刑事罰を受けるおそれがあるので、十分ご注意ください。
お問い合わせください。
4、能力の低い社員への対応に悩んでいる企業は弁護士に相談を
能力の低い社員を抱えていて、どのように対処すべきか悩んでいる企業は、弁護士に相談することをおすすめします。
能力の低い社員への対応につき、弁護士に相談することの主なメリットは以下のとおりです。
- トラブルのリスクを想定しつつ、適切な対応についてアドバイスを受けられる
- 有効に解雇できるかどうかを、法的な観点から判断してもらえる
- 解雇後に社員とのトラブルが発生した場合も、スムーズにサポートを依頼できる
弁護士と顧問契約を締結すれば、能力の低い社員への対応を含めて、人事労務に関する悩みをいつでも相談できます。労務体制を強化したい企業は、顧問弁護士との契約をご検討ください。
5、まとめ
能力の低い社員がいる場合は、まず本人に問題点を伝えて改善指導を行いましょう。また、能力を発揮できるポジションを探すために、配置転換を行うことも選択肢のひとつです。
改善指導や配置転換が奏功しない場合は、退職勧奨や解雇を検討しましょう。ただし、解雇には厳しい規制が適用されるため、事前に弁護士へ相談することをおすすめします。
ベリーベスト法律事務所は、人事労務に関するご相談を随時受け付けております。能力の低い社員への対応に悩んでいる企業は、経験豊かな弁護士が適切な対処法をアドバイスいたしますので、お早めにベリーベスト法律事務所へご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています