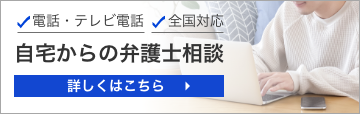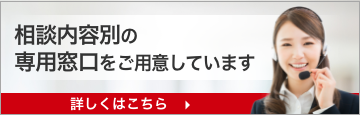妊婦に残業させるのは違法? 妊産婦保護の制度について解説
- 労働問題
- 妊婦
- 残業
- 違法

職場に妊娠した女性労働者がいる場合、企業には、労働基準法の「母性(妊産婦)保護規定」に基づき、特別な配慮が義務付けられています。
妊産婦に対して違法な残業命令や不利益取り扱いをした場合、企業にペナルティが課されるおそれがあるため、事前対策を講じることが大切です。
今回は、妊婦に残業をさせることの違法性や妊産婦保護制度について、ベリーベスト法律事務所 池袋オフィスの弁護士が解説します。
1、妊婦に残業させてはいけない? 妊娠中の職場環境とは?
妊娠中の労働者がいる場合、労働基準法、男女雇用機会均等法、厚生労働省の省令などにより、職場環境に関して以下のような制限が設けられています。
-
(1)時間外・休日労働・深夜業の制限
妊婦の労働者、従業員に対して、直ちに時間外労働、休日労働、深夜労働が禁止・制限されることはありません。
しかし、時間外労働、休日労働、深夜労働は、妊婦の身体に負担がかかるため、妊婦本人から請求があった場合、時間外労働、休日労働、深夜労働をさせることはできません(労働基準法66条2項、3項)。 -
(2)変形労働時間制の適用制限
変形労働時間制は、職場の繁忙期や閑散期に合わせて、時間を調整しながら働くことが可能な制度です。
しかし、妊婦から請求があった場合には、1日8時間・1週40時間の法定労働時間を超えて残業をさせることはできません(労働基準法66条1項、32条1項及び2項)。 -
(3)軽易業務転換
軽易業務には、重い荷物の運搬などが含まれることもあります。そのため、業務内容によっては妊婦の身体に負担がかかる可能性があります。この場合、妊婦から請求があった場合には、他の軽易な業務に転換させなければなりません(労働基準法65条3項)。
従業員から妊娠の報告と軽易業務への転換希望があった場合には、以下の事項を検討しましょう。
- 転換先の業務の有無、内容
- 配置転換の日
- 現在の業務の引き継ぎ方法
- 転換後の賃金
特に、賃金が変更になる場合は、差額に関して配慮するよう注意が必要です。
-
(4)危険有害業務の就業制限
妊婦を危険有害業務に就かせることは法律によって禁止されています(労働基準法64条の3)。危険有害業務の例としては、放射線業務や有害ガスを発散する場所での業務、重量物を取り扱う業務などがあります(同条1項)。
なお、妊婦以外の女性についても妊娠または出産機能にとって有害である業務に就かせることは禁止されています。
2、妊婦に違法な残業命令を出さないための対処法とは?
上記のように妊婦に対しては、妊娠中の身体への負担を軽減するためにさまざまな規制が設けられています。企業としては、妊婦に対し、違法な残業命令を出さないようにするためにも以下のような対処が求められます。
-
(1)従業員の労働時間を適正に把握・管理する
まずは、従業員の労働時間を適正に把握・管理することが必要です。
企業が把握・管理すべき労働時間とは、
- 従業員の労働時間
- 休日労働の時間
- 時間外労働の時間
などが挙げられます。
労働時間の把握・管理は、労働安全衛生法でも義務付けられていますので、自社でしっかりと対応できているかどうかも含め、確認することが大切です。 -
(2)母性保護規定の対象となる従業員かどうかを確認する
妊娠・出産の状況によって母性保護規定の内容が異なるため、確認しておきましょう。
対象となる従業員 保護の内容 根拠法令 妊娠中~産後 ① 産前・産後の休業や時間外労働の制限など
② 妊産婦のための健康診査を受ける時間の確保① 労働基準法 第66条(時間外労働の制限)
② 男女雇用機会均等法 12条出産後1年以内 時間外労働・深夜業務の制限など 労働基準法 第66条(深夜業務の制限) 産前6週間・産後8週間 産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)および産後8週間の休業 労働基準法 第65条(産前産後休業)
また、男女雇用機会均等法では、妊娠中・産前産後にかかわらず、こうした保護措置を理由とする解雇や降格などの不利益な扱いを禁止しています。詳しくは3章で解説します。
-
(3)業務命令の適法性を確認する
母性保護規定の対象となる労働者から請求があった場合には、当該労働者に対して残業命令を出すことはできません(労働基準法66条1項から3項)。
職場内の人員配置などを見直して、対象労働者に残業をさせなくても対応できる体制整備を進めていきましょう。
3、不利益取り扱いやマタニティハラスメントをした場合にはペナルティがある
妊娠・出産を理由とする不利益取り扱いやマタニティハラスメントをすると企業に対してペナルティが課されるリスクがあります。
-
(1)妊娠・出産を理由とする不利益取り扱いにあたるケース
男女雇用機会均等法や育児・介護休業法では、妊娠・出産などを理由とする不利益な取り扱いが禁止されています(男女雇用機会均等法9条3項、育児・介護休業法10条)。
たとえば、妊婦に対して以下のような取り扱いことは違法です。
- 妊娠したことを理由に解雇する(労働基準法19条)
- 妊婦検診を受けに行くために仕事を休んだことを理由に退職を強要する
- つわりや切迫早産で仕事を休んだことを理由に減給する
- 産前産後休業をとったことを理由に正社員からパート社員になるよう強要する
このような不利益取り扱いにより法違反となれば、労働基準監督署による行政指導の対象になりますので、助言・指導・勧告を受け、企業名を公表されるリスクがあります。
また、不利益取り扱いに該当する処分は、違法・無効となりますので、処分の無効を求めて従業員から訴えられるリスクもあります。 -
(2)不利益取り扱いとは別にハラスメント行為も禁止されている
男女雇用機会均等法や育児・介護休業法では、企業に対し、職場における妊娠・出産などに関するハラスメントを防止する措置を講じることを義務付けています。
そのため、妊娠を理由に以下のような言動をとると、マタニティハラスメントとして違法になる可能性があります。
- 解雇を示唆するようなことをいう
- 正社員からパートになるよう求める
- 産前産後休業の利用を控えるようすすめる
- 産前に行っていた仕事を取り上げ、雑用をさせる
- 「この忙しい時期に妊娠するなんて信じられない」などの暴言を吐く
職場内でこのようなハラスメントが生じているにもかかわらず、企業が適切な対応をとらない場合には、安全配慮義務違反を理由として企業の責任を追及されるリスクがあります。
また、ハラスメントに関する相談窓口が設置されていない場合には、行政指導の対象になりますので注意が必要です。
お問い合わせください。
4、労務管理を弁護士に相談すべき理由とは?
従業員とのトラブルを回避するためには、労務管理を徹底することが求められます。特に、女性労働者を雇用している場合には、妊娠・出産などをきっかけにトラブルが生じる可能性がありますので、しっかりと対策を講じていく必要があります。
そのためには、労働問題の解決実績が豊富な弁護士のアドバイスやサポートが重要になりますので、まずは相談してみることをおすすめします。
-
(1)適切な職場環境を整備するためのアドバイスを受けることができる
職場内に妊娠した女性労働者がいる場合、労働基準法、男女雇用機会均等法、厚生労働省の省令による制限を満たす形で職場環境の整備を進めていかなければなりません。法律上義務付けられているというのも理由ですが、優秀な女性労働者の離職を防ぐという意味でも女性が働きやすい職場環境を整備することが重要です。
法律上の規制をすべて把握するのは非常に困難といえます。弁護士であれば企業の実情を踏まえて、注意すべき規制や対応策のアドバイスが可能です。効率的に職場環境の整備を進めていくことができるでしょう。 -
(2)マタハラを未然に防ぎ、労務トラブルを回避できる
妊娠していることを理由とするハラスメント、いわゆる「マタニティハラスメント」にも気を付けなければなりません。
妊婦に対する不適切な言動は、マタハラと評価され、悪質なマタハラに対しては、女性労働者から慰謝料請求をされるリスクがあります。また、マタハラが横行する職場では、女性労働者が次々と離職するおそれもあります。
弁護士は、ハラスメントの相談窓口の設置やハラスメント研修の実施などにより、労務トラブルの回避に向けたサポートを行うことができます。 -
(3)万が一トラブルになった場合でも対応を依頼できる
従業員との間でトラブルが発生した場合、その対応に時間や労力を割かなければならないため、本業に支障が生じるおそれがあります。
弁護士は、労働者の説得や交渉を企業担当者に代わり行います。労働法や労働問題の裁判例に基づいた適切な解決が期待できますので、自社で対応するのが難しいと感じるときは、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
5、まとめ
妊婦を保護するために労働基準法、男女雇用機会均等法、厚生労働省の省令ではさまざまな規制を設けています。違反しないためにもしっかりと対応していくことが必要です。
労働者との労務トラブルを回避するには、労働問題の解決実績がある弁護士のサポートが大切です。ベリーベスト法律事務所では月額固定で始められる顧問弁護士サービスをご用意しています。労働問題のお悩みに寄り添い、さまざまなアドバイスでサポートいたします。
労務トラブルに対応できる顧問弁護士をお探しの方は、ベリーベスト法律事務所 池袋オフィスまでお気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています