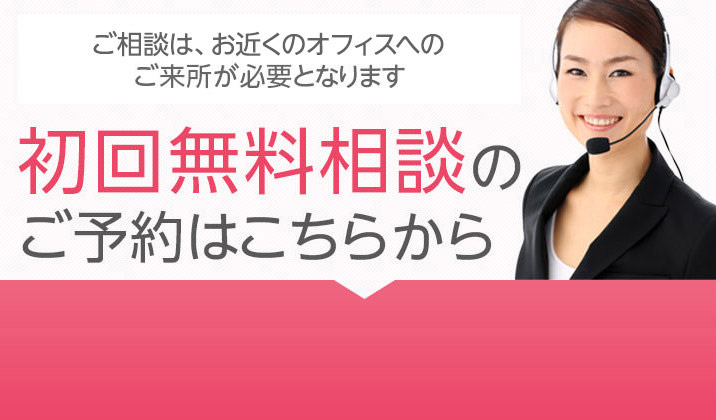親権の放棄は可能? 親権者の決定や離婚後の養育費請求
- 親権
- 親権
- 放棄

豊島区が発表している「としま政策データブック2024」によると、令和4年、豊島区では377組の夫婦の離婚が成立しました。
子どもがいる夫婦が離婚する場合、親権者を決める必要があります。親権をお互いに譲りたくないという夫婦がいる一方で、親権を放棄したいと考える方もいるでしょう。
では、親権を放棄する・放棄させることは可能なのでしょうか? その場合、親権を放棄した側に養育費を請求することはできるのでしょうか? ベリーベスト法律事務所 池袋オフィスの弁護士が解説します。


1、親権を放棄する・放棄させることは可能?
親権を放棄する・相手に放棄させることはそもそもできるのでしょうか?まずは親権の基本からみていきましょう。
-
(1)そもそも親権とは?
「親権」とは、未成年の子どもの利益を守るために、子どもの財産を管理したり、監護・教育を行ったりする権利・義務の総称です(民法第820条)。婚姻中は夫婦共に親権を持ち(民法第818条第1項)、共同で親権を行使しますが(同条第3項)、離婚をする場合、どちらかを親権者に定める必要があります(民法第819条第1項、第2項、第5項)。
親権には、「身上監護権」と「財産管理権」という2つの権利義務が含まれており、親権者がどちらの権利義務も持つのが原則です。ただし、親権者ではない方の親が「身上監護権」を持つことも可能で、その場合に身上監護権を持つ親を「監護権者」といいます。
これら2つの権利義務の内容についてみていきましょう。
① 身上監護権
「身上監護権」は、未成年の子どもを心身ともに健全に成長させるために監護・教育する権利義務のことです。身上監護権には以下の4つの権利義務が含まれています。- 監護教育権
親権者は子の人格を尊重し、年齢や発達の程度に配慮すること、また体罰や心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならないという義務 - 居所指定権
親権者が子どもの居所を指定する権利 - 職業許可権
子どもが職業を営むことを親権者が許可・制限する権利 - 身分行為の代理権
子どもが養子縁組などの身分行為を行う際に、親権者が同意・代理する権利
② 財産管理権
「財産管理権」は、未成年の子どもの財産を管理したり、子どもの法律行為を同意または代理したりする権利義務のことです。
未成年者は法律上、親権者の同意を得なければ法律行為ができません。そのため、親権者は子どもの法律行為(売買契約や婚姻など)に対する同意権や代理権を持ちます。
これにより、たとえば高額な商品を子どもが購入してしまった場合、親権者が売買契約を取り消すことができるのです。 - 監護教育権
-
(2)原則として親権は放棄できない|親権の辞任・変更は可能
親権は、親にとって子どもを監護・教育するための権利であり、義務でもあります。従って、原則として放棄することはできません。
ただし、裁判所で親権の辞任・変更をすることはできます。親権の辞任・変更とはどういうことなのか、詳しくみていきましょう。
① 親権の辞任
親権の辞任とは、親権者に「やむを得ない事由」がある場合、家庭裁判所の許可を得て親権者の地位を辞めることです。
「やむを得ない事由」(民法第837条)とは、たとえば子どもを養育できないほどの重病を患っている、犯罪で長期間服役する、といった客観的に子どもの養育に適さない事態のことです。
一方的な「放棄」は法律上認められませんが、やむを得ない理由があれば、子どもの利益を考慮した上で、適切な手続きをした「辞任」は認められます。
なお、単独親権者が親権を辞任するためには、未成年後見人を選任する必要があります。
② 親権の変更
「辞任」以外にも、親権者を元配偶者に「変更」することも可能です。その場合は、当事者間で合意に至っている場合でも、家庭裁判所で調停あるいは審判を行う必要があります。
2、離婚の際に、親権を放棄する・放棄させるには?
では離婚の際に、親権を放棄する、あるいは相手に放棄させるにはどうすればいいのでしょうか?
まず前提として、離婚する場合は単独親権となります。「単独親権」はどちらかの親のみが親権を持つことです。
そのため、離婚で親権を放棄する・放棄させるには、「親権者決め」が重要になります。
では、親権者を決める方法・手順についてみていきましょう。
-
(1)夫婦間協議
まずは父母の話し合いで親権者を決めていきます。親権を放棄したい場合は相手に親権を譲ることを伝え、親権を放棄させたい場合は自分が親権者になりたいことを伝え、相手を納得させることが大切です。
話し合いで親権者が決まれば、後のトラブル防止のために適切な離婚協議書を作成しておきましょう。できれば「公正証書」にしておくことがおすすめです。
「公正証書」とは公証人が作成する公文書のことで、証拠力が高いという特徴から、後のトラブル防止に役立ちます。親権者の他にも養育費や面会交流など、その他離婚条件について取り決めた内容も、公正証書にしておきましょう。 -
(2)調停
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に「調停」を申し立てる必要があります。「調停」は、調停委員会(裁判官と調停委員で構成)の仲介の元、アドバイスを受けたり和解案を示されたりしながら、話し合いで紛争を解決していく制度です。
離婚の際に親権について争いがある場合、「離婚調停」で親権者について決めていきます。 -
(3)訴訟
「離婚調停」がまとまらなかった場合、「離婚訴訟」を提起することになります。なお、「すぐに訴訟を起こしたい!」と思う方もいるかもしれませんが、離婚訴訟は「調停前置主義」であり、まずは離婚調停を行わなくてはなりません。
離婚訴訟では、当事者の主張や、その主張を裏付ける証拠・資料を元に、裁判官によって争いに関する判断が下されます。親権について争いがある場合、裁判官がどちらを親権者にするか決めるということです。
ちなみに、現在の法律では離婚後の親権については「単独親権」しか認められませんが、令和6年5月17日に「共同親権」が選択できるようになる改正民法が成立しました。令和8年5月24日までに施行されるため、改正民放施行後は離婚後の親権について「共同親権」か「単独親権」かを選択できるようになります。
なお、改正法前に離婚が成立し、親権者が決まったからといって、この改正法が無関係というわけではありません。たとえば、ご自身が単独親権者になって改正法施行前に離婚していた場合も、親権者変更の手続きにより家庭裁判所が認めれば共同親権に変更できるようになるからです。
現在は「単独親権」を選択している場合でも、改正法が施行されれば、「共同親権」へ変更する協議ができるようになることを覚えておきましょう。まずはお気軽に
お問い合わせください。メールでのお問い合わせ営業時間外はメールでお問い合わせください。
3、親権を放棄した親にも養育費は請求できる
親権者でなくなった側の親(非親権者)であっても子どもへの扶養義務はなくならないため、養育費を支払う義務があり、子どもは養育費を受け取る権利があります。それゆえに、親権者は子どものために非親権者に対して養育費を請求することができるのです。
養育費の金額は話し合いで自由に決めることができますが、話し合いでは「養育費算定表」で算定した金額を参考にするケースが多いです。
「養育費算定表」の内容と、計算方法を解説します。
-
(1)養育費算定表とは
「養育費算定表」は家庭裁判所が公表している計算表のことです。夫婦の収入(年収)や未成熟子の年齢、人数を考慮して養育費の金額を簡単に計算することができます。
-
(2)養育費の計算方法
「養育費算定表」の計算は、「両親双方の年収」が基準となっていて、子どもの年齢・人数に応じて9つに分かれている表から適切な表を選択します。「両親双方の年収」に応じた養育費の金額の目安が計算できるため、「年収」の金額の求め方が重要です。
年収の求め方は「給与所得者」の場合と「自営業者」の場合で異なります。
給与所得者の場合の年収は、源泉徴収票の「支払金額」欄を確認することで簡単に把握することができますが、自営業者の場合は税法上の修正を考慮して年収を計算しなければなりません。
自営業者の年収は、確定申告書に記載されている「課税される所得金額」に、「社会保険料控除以外の所得控除の額」を加算することで算出できます。
算出したそれぞれの年収に応じて、養育費の目安を算出しましょう。
ちなみに、養育費の支払いには原則贈与税がかかりません。
また、子どもには養育費を受け取る権利だけでなく、親権を放棄した親の財産を相続する権利もあります。離婚後も、非親権者と子どもが親子であることは変わらないため、子どもは親権者でなくなった親の財産も相続することが可能です。
4、親権を放棄する・放棄させる場合は、弁護士に相談すべき
親権を放棄する・放棄させる場合、まずは弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士に相談することで、親権の放棄に関する適切なアドバイスを受けられる他、親権に関する交渉を任せられるため、ご自身で全て対応するよりも早い解決が期待できます。
また、協議が決裂し、調停や訴訟に発展した場合の手続きも一任できるというメリットもあるでしょう。
その他にも、親権や養育費について決まった後の養育費の扱いについてのアドバイス受けることもできます。親権についてお困りの際は、早い段階で弁護士に相談するようにしましょう。
5、まとめ
親権は、親にとって子どもを監護・教育するための権利であり、義務でもあることから、原則として放棄することはできません。ただし、やむを得ない事由があり裁判所で認められれば親権の辞任・変更をすることはできます。
親権を放棄した親にも養育費を支払う義務があるため、まずは「養育費算定表」を参考に話し合いを行い、決裂した場合は調停・訴訟で決めていきましょう。
ご自身だけで対応をすると、自分にとって不利な結果になってしまうケースもありますので、早い段階で弁護士へ相談することをおすすめしています。
その際はぜひ、ベリーベスト法律事務所 池袋オフィスの弁護士にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
- |<
- 前
- 次
- >|